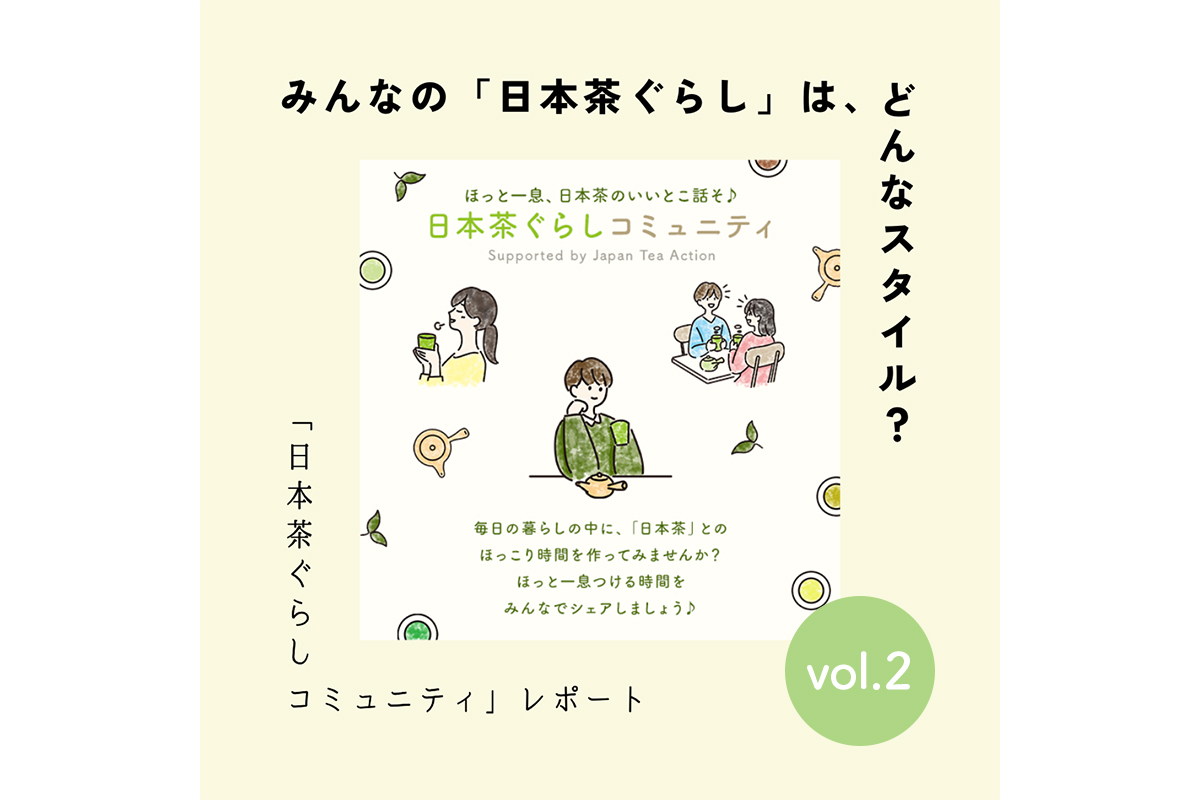富士山の麓から世界へ。「富士山抹茶」が描く、お茶と地域の未来地図
富士山の麓、豊かな自然とともに広がる静岡県富士市のお茶畑。消費量の低下、生産者の高齢化など、お茶をはじめとする一次産業は様々な課題を抱えており、茶畑の風景も減少しているのが現実です。そんな中、「伝統を未来へ、豊かさを日常へ」をビジョンに掲げ、お茶業界に新たな風を吹き込む「株式会社EN.」の共同代表、大坂さんと稲生さんにお話を伺いました。“生産者が正当に評価される文化を築く”という想いを胸に、地域の価値を創造するための取組をご紹介します。

写真左:大坂 嘉謙(おおさか よしかね) / 株式会社EN. 代表取締役CEO
静岡県富士市出身。立命館大学体育会サッカー部に所属。静岡銀行で地域経済に携わったのち、ファーストキャビンHDにて不動産と経営のスキルを学び、将来の事業基盤を築く。2024年、株式会社EN.を創業。地域活性化と静岡茶の価値向上、富士市のまちづくりに取り組む。現在は富士山抹茶(Mt.FUJI MATCHA)のブランド確立に励んでいる。
写真右:稲生 大輔(いのお だいすけ) / 株式会社EN. 代表取締役COO
大阪府富田林市出身。立命館大学体育会サッカー部に所属。共同代表の大坂と出会い、静岡県富士市のファンになる。株式会社キャンサースキャンにて、自治体の予防医療にまつわる事業のプロジェクトリーダーとして事業の企画から実行までを担当。全国津々浦々に出向き、地方の魅力と可能性を感じる。2024年、株式会社EN.を創業。富士市の活性化と茶産業の発展を目指し、富士山抹茶のブランドの確立、抹茶を通じて人とお金の流れを作るまちづくりに取り組む。
大学の出会いから始まった、富士市での挑戦へ
―― 二人の出会いは、大学時代だったそうですね。
大坂さん:そうなんです。大学のサッカー部で一緒だったんですが、最初はお茶とは全く関係なく、ただただ仲が良くて。「社会人になっても一緒に何かやれたらいいね」って話していたくらいです。その後、自分は静岡の富士市出身で、家業である不動産業のため、東京で修行も兼ねて働いていました。一方で、稲生は地域活性化事業のような仕事をしていて。
稲生さん:仕事柄、僕は全国を飛び回っていたので、地域ごとの魅力を大坂によく話していました。その中で「富士市ってすごくいい所だと思う」って話をしたんです。富士山、川、海があって、水もきれいで、食も豊かですしね。
大坂さん:そこから二人で「じゃあ富士市で何かやってみよう」という流れになりました。
―― 大学時代から続く素敵なご縁ですね。
大坂さん:富士市について調べていく中で、お茶産業の衰退、という問題に辿り着いたんです。直接お茶農家さんに会って話を聞き、茶葉の買い叩き、後継者不足など、色んな課題があることに気付きました。
富士の抹茶に可能性を見出した仲間との出会い
稲生さん:様々な話を聞いて、僕たちがお茶で何かやるんだったら“富士の抹茶”があったら需要がありそう、と話をしてたんですよ。だけど、富士市には抹茶がほとんどなかったんです。
―― 意外ですね。なぜ抹茶を作っていなかったんでしょうか?
大坂さん:静岡は長年お茶の王国だったので、もちろん富士市も「煎茶」の生産は盛んです。そのまま煎茶を作り続けていたら、気付けば産業が衰退し、高齢化が進み、跡継ぎがいない。そんな状況で新しい挑戦をする人も少なくなっていたんですよね。
稲生さん:富士市は静岡の東側にあって、お茶の収穫が遅くなりがち。既に西側で十分なお茶が出回っている時期に収穫するので、価格が付きにくいという問題もあります。「良いお茶を作っているのに、なぜ売れないのか」と悩む農家さんが多いのが現状です。
大坂さん:そんな時、父の知り合いのお茶農家さんで「富士市で育てた抹茶を世界に発信したい」と挑戦を始めた方がいると聞いて、すぐに会いに行きました。農家さんからは、「富士で育つオーガニックの抹茶が世界に出られると思っているから、富士市で抹茶をつくる。だけど売ってくれる人がいない。」という話をしてくれて。それを聞いた瞬間に「じゃあすぐに会社作るので、一緒にやらしてください」って。

稲生さん:僕たちは売る力がある。農家さんは作る力がある。その役割がピタリと噛み合ったので。そんな始まりから今日まで、そのお茶農家さんと一緒に「富士山抹茶」を作っています。
―― 「富士山抹茶」という名前は記憶に残りますね。富士山とお茶畑、ザ・日本の景色です。
大坂さん:やっぱり1番の特徴は「富士山で育っている」というところです。富士山の麓の土壌はミネラルが豊富なので、お茶も栄養価が高いのではと言われています。海外ではスーパーフードとして人気の抹茶ですが、富士山抹茶はさらに一歩先を行っているかもしれません。

稲生さん:富士山の雪解け水が海に向かってずっと流れていくことで、富士市の土地は常にしっとりしていて、良い土壌ができているようです。もちろん農家さんの技術力があってこそですが、富士山の麓という土地柄も、大きな後押しになっていると思います。
―― ご縁のあったお茶農家さんは、どうして抹茶に挑戦しようと?
大坂さん:出会った農家さんたち——2つのお茶園さんの2代目のお二人は、茶畑を守りたいという強い想いを持っていました。お茶業界の衰退の中、このままじゃ茶畑が負の遺産になってしまう。茶畑はもちろん、お茶を広めていきたいというモチベーションがあった二人は、ここから挑戦するものとしてオーガニック抹茶に行きついたようです。
稲生さん:彼らは40代で、自分たちで挑戦できるだろうということで。富士市の異端児というか、周囲からは「何やってるの?」って言われることも多いですが、それでも貫いた。その姿勢に僕たちも共鳴しました。

抹茶を通して富士を知ってもらうために —— 「富士山抹茶」が目指す未来
―― お二人が手がけているのは、単に「お茶を作って売る」ということではないと感じるのですが、どのような展開を考えていらっしゃいますか?
稲生さん:そうですね、自分たちは抹茶そのものを売るというより、「抹茶を通じて富士市を知ってもらって、足を運んでもらう」という観点で動いています。東京のお店で扱っていただいたり、オンライン販売もしていますが、あくまで目的は“人が動く”ことです。
大坂さん:例えば、富士山の麓の茶畑で茶会を開くイベントなど、抹茶のPRだけじゃなくて、「富士山が広がるこんなに美しい場所で、こんな風にお茶を楽しめる」というところを価値化して伝えたい。抹茶そのものというより、“地域に根ざしたブランドづくり”ですね。

―― 今後の展開として、どんなビジョンを描いているんでしょうか?
大坂さん:最終的には、観光で来た人が「ここに住みたい」と思えるような魅力的な街にしていきたいです。まずは1、2泊で滞在してもらえるように、宿泊施設を作りたいですね。富士市って、どこにいても「富士山の中にいる」ような感覚があるんです。まさにその富士山と茶畑が一望できる場所に、オーベルジュスタイルの宿泊施設を作ることが目標の一つです。
稲生さん:大坂は不動産やホテルのバックグラウンドがあり、僕は地方で人を動かすことを仕事でしてきました。だからこそ、お互いの強みを生かして、今は抹茶を起点に富士市をどう魅力的に見せるかという構想を作っています。
大坂さん:たまたまうまく噛み合った感じです(笑)。
EN.の歩みがわかる、「富士山抹茶」お披露目野点茶会の様子
「伝統を未来へ、豊かさを日常へ」——生産者を讃える文化を築く
大坂さん:僕らEN.のビジョンは、「伝統を未来へ、豊かさを日常へ」です。これはもう、自分たちが本当にやりたいことでもあるんですが、お茶をはじめとする日本の伝統文化の価値を、未来につないでいくこと。それが結果的に、地域や日本全体の日常をもっと豊かにしてくれるんじゃないかと思っているんです。
稲生さん:そのためのミッションとして「生産者の努力と情熱を正当に評価して、アーティストのように讃える文化を築きたい」と考えています。たとえば画家って、絵の価格は“言い値”で買ったりする世界ですよね。でも農家さんを含む一次産業の方はというと、どうしても「安く買い叩く」という構造になってしまっている。それでは続かないし、未来に伝わらないので。
―― アーティストのように、という視点は新鮮です。
大坂さん:農家さんの茶葉がきちんと価値をもって評価される社会にしていきたいんです。先程の画家の例えのように、言い値で買われるような文化が、お茶の世界にもあっていいはず。EN.の活動を通じて、富士山の麓からそんな文化がつくれたら、きっと全国にも伝わるはずです。